近年、資産運用や節税対策の手法として「マイクロ法人」を活用するケースが増えています。
個人投資家やサラリーマンにとって、法人を設立することで税制上のメリットや資産管理の効率化が期待できるため、非常に注目されています。
・マイクロ法人を利用した資産運用の主なメリットと注意点
・マイクロ法人の作り方
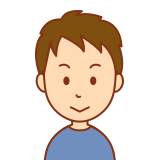
難しそうだね
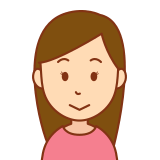
ひとつずつ説明します

マイクロ法人での資産運用のメリット
1. 税制上の優遇
- 低い法人税率
マイクロ法人の場合、個人の所得税率と比較して法人税率が低く設定されています。
例えば、課税所得が800万円までは約15%、800万円を超えると23.2%程度となるため、節税効果が期待できます。 - 経費計上の幅が広い
個人では経費として認められにくい支出も、法人経費として計上することが可能です。
これにより、実質的な税負担を軽減できる仕組みになっています。
2. 資産管理の効率化
- 減価償却や支払利息の経費計上
例えば、役員の自宅を法人所有にすることで、減価償却費や支払利息を経費として計上でき、資産管理の効率が向上します。 - 投資関連経費の広範な計上
投資活動に伴う各種経費が幅広く認められるため、経費の活用によって節税効果をさらに高めることが可能です。
3. 社会保障の充実
- 厚生年金への加入
マイクロ法人のオーナーは、役員報酬を受け取ることで給与所得者となり、厚生年金などの社会保険に加入することができます。
これにより、将来的な年金受給額の増加や各種社会保障の恩恵を受けることが可能です。
4. 損失の繰越
- 最大10年間の損失繰越
投資における損失が発生した場合、その損失を最長10年間にわたって繰り越すことができるため、将来の税負担を平準化する効果が期待されます。
マイクロ法人作ってない人=資本主義における情弱確定 pic.twitter.com/rY5zN7VKfF
— みるぼん@スモビジ (@milbon_) February 8, 2025
最近では自分でかんたんマイクロ法人設立【マネーフォワード クラウド会社設立】で簡単に会社が設立できるようになりました。
マイクロ法人活用時の注意点

1. 会社資産の私的利用制限
法人化すると、法人の収益は個人の自由な私的利用が制限されます。
会社資産と個人資産の区分を明確にし、適切な管理が必要です。
2. 初期費用と運営コスト
法人設立時には初期費用が発生し、さらに運営コストも必要です。
ただし、資産運用に特化した法人の場合、比較的低コストで始められる点は魅力です。
3. 収益目標の設定
法人税の負担を抑えるためには、経費と同額の収益を目標にし、最終的な利益をゼロに近づける戦略が有効です。
この点は、計画的な経営と収支管理が求められます。
4. 適切な業種選択
資産管理・運用業は、在庫や仕入れのリスクが少ないため、マイクロ法人に適した業種と言えます。
しかし、事業内容と税務上の取り扱いについては、事前に専門家と十分に相談することが重要です。
公務員を辞めると決めた時に、最初の壁になったのが退職後の健康保険の選択でした。
— なめねこ😸|公務員でもできる富裕層の投資 (@nameneko_omocha) January 25, 2025
国保は高いし、任意継続もそれなりの負担…。
そこで、Xの先輩方を参考にマイクロ法人を設立して社保に加入しました。
法人の設立や維持にコストはかかりますが、それを考慮しても安くて有利。…

ここまでのまとめ

マイクロ法人を活用した資産運用は、税制上の優遇や資産管理の効率化、社会保障の充実など、多くのメリットがあります。
しかし、法人化に伴う初期費用や運営コスト、会社資産の私的利用制限といった注意点も存在します。
成功するためには、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に運用戦略を練ることが肝要です。
ぜひ、この記事を参考に、マイクロ法人を活用した資産運用について深く検討してみてください。
【マイクロ法人の賢い報酬設定】
— 不動産投資家MASA (@2103ou_masuke) January 27, 2025
自分への役員報酬は少ないほど良い。
なぜなら社会保険料は30%もかかるから。
しかも今後も社会保険料は上がり続ける。
そして銀行も法人に利益残した方が喜ぶ。
ただそのためには、個人でもある程度物件を所有しておく必要アリ(続

マイクロ法人の作り方
マイクロ法人の作り方については、こちらも参照ください。
設立手続きや必要書類について詳しく説明しています。
マイクロ法人とは
小規模な運営:
マイクロ法人のメリット

社会保険料を自分でコントロールできる
最大のメリットは、社会保険料を自分でコントロールできることです。
会社員の場合、給料から自動的に税金や社会保険料が天引きされます。
所得税
法人税、
雇用保険、
介護保険など
しかし、法人を持つことでこれらの問題を解消できます。
社会保険料は4〜6月の給料額で決まるため、
この期間の給料を調整することで1年間の保険料をコントロールできます。
法人で最低限の報酬を設定することで、支払う社会保険料を最低ランクに抑えつつ、手厚い公的保険の恩恵を受けることができます。
高所得者でも低所得者でも、社会保険の恩恵は平等に受けられます。
公的保険のありがたみ
日本の社会保険制度は非常に手厚く、病気や怪我をしても現役世代は3割を支払うだけで済むというメリットがあります。
民間の保険と比較しても、そのコストパフォーマンスは非常に高いです。
自営業やフリーランスの方にとって、こうした公的保険の存在は非常にありがたいものです。
税金のコントロール
法人を持つことで、税金をある程度コントロールすることができます。
個人事業主の場合、売上がそのまま所得として扱われるため、所得税の負担が大きくなります。
しかし、法人の場合、会社の経費として計上できる項目が多いため、課税所得を減らすことができます。
また、法人税率も所得税率より低く設定されているため、全体の税負担を減らすことが可能です。
厚生年金払うのやめたい
— おじモニ@無能CRA (@CRA_ojiji) January 20, 2025
→会社員辞めたい
→個人事業主になりたい
→国民年金のみ
社会保険料安くしたい
→会社員辞める
→マイクロ法人作る
→国民健康保険料最低額
結論
個人事業主になってマイクロ法人を作り、月に数万円の報酬をマイクロ法人から受け取るのが最適解

マイクロ法人のデメリット

もちろん、マイクロ法人にもデメリットがあります。以下に主なデメリットを挙げます。
赤字でも法人住民税・県民住民税を払う必要がある
法人を持つと、たとえ赤字であっても法人住民税と県民住民税を払わなければなりません。
最低でも年に7万円の住民税が必要です。
法人を廃業しない限り、この税金は払い続けなければなりません。
また、廃業にも手続きや費用がかかります。
法人住民税や県民住民税の支払いは、収益が少ない時期でも継続して必要になるため、一定のキャッシュフローを確保しておく必要があります。
毎年確定申告が必要
法人を持つと、売上がなくても毎年確定申告を行う必要があります。
確定申告は、事業年度が終了した後に税務署に対して行うもので、法人税や住民税の申告が必要です。
これには一定の時間と手間がかかり、特に事業規模が大きくなると、税理士などの専門家に依頼する必要が出てくる場合もあります。
確定申告の手続きには、売上や経費の記録を正確に行う必要があり、これを怠ると罰則を受ける可能性もあります。
法人の設立や運営にかかる手間と費用
法人を設立するには、定款の作成や登記手続きが必要で、これには一定の費用と時間がかかります。
法人設立後も、定期的な報告義務や各種手続きが求められます。
例えば、役員の変更や事業内容の変更があった場合は、法務局への届け出が必要です。
また、社会保険や労働保険の加入手続きも法人化すると必須となり、これらの手続きも時間と労力を要します。
FIREしてから𝕏フォロワーさんからの情報収集で一番感謝していること。それはマイクロ法人を設立することで退職後の年間の支出が大きく削減できるというお話。削減額は会社の社会保険任意継続と比べて月間7万円。法人の支出は会社設立に7万、運営に7万(法人住民税)なので、2か月で回収できることにな…
— ひろ@サイドFIREのリアルを届けます (@Hiro_HASYG) February 13, 2025
まとめ

今回はマイクロ法人を6年間運営して感じた良い点を中心にご紹介しました。
マイクロ法人を持つことで、社会保険料や税金をコントロールできるという大きなメリットがありますが、赤字でも住民税を支払う必要があることや、毎年確定申告が必要なことなど、デメリットもあります。
個人事業主としてスタートしたばかりの頃は、年7万円の住民税は厳しいかもしれません。
そのため、まずは個人事業主として売上をしっかりと作り、その後に法人化を検討するのが理想的です。
法人化には設立にかかる時間や手続きが必要ですが、節税効果を考えると一考の価値があります。
法人を設立することで得られるメリットを最大限に活かし、ビジネスの発展に繋げてください。
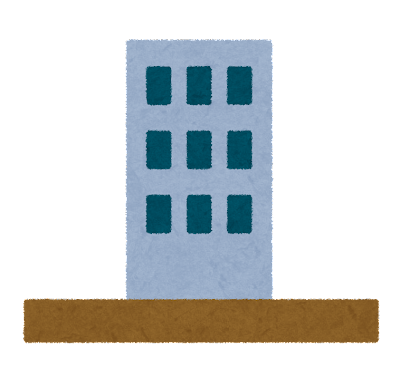



コメント