「毎月分配金がもらえるETFがあったらいいのに…」そう思ったことはありませんか?
QYLDは、高い分配金利回りを誇る米国ETFで、投資初心者でも比較的手軽に始められるのが特徴です。
NASDAQ100を対象としたカバードコール戦略を活用し、株価の値上がり益よりも安定した分配金を重視した設計になっています。
しかし、「QYLDって本当に儲かるの?」「リスクはないの?」と不安に思う方も多いはず。
そこで本記事では、QYLDの仕組みやメリット・デメリット、購入方法、そして投資する際の注意点まで詳しく解説します!
投資初心者でも分かりやすい内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
✅ QYLDとは? 分配金の仕組みやカバードコール戦略の特徴を解説
✅ 投資初心者に向いている理由 少額投資のメリットや安定したキャッシュフロー
✅ QYLDのメリット・デメリット 高配当の魅力とリスクを比較
✅ 購入方法とおすすめ証券会社 取引手数料や最低投資額をチェック
✅ 投資時の注意点 再投資戦略・暴落時のリスク管理・年金代わりに活用する方法
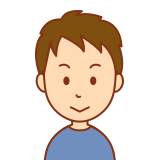
僕が持っているQYLDについて書きました
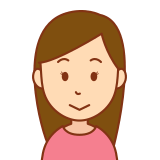
2018年から持ってるけど売らないのね
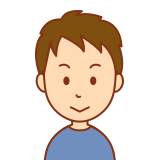
証券口座がすでにある方もNISA取引手数料無料の楽天証券がオススメですよ
- 🚀初心者でも使いやすい
- 🌏 豊富の株式の取り扱い
- 📈 NISA専用のページがわかりやすい
- 💰 楽天ポイントで投資可能
- 🚀 スマホでも簡単に売買できる便利な取引ツール
- 🏦 楽天銀行と連携すれば、スムーズに資金移動もOK!
QYLDブログとは?分配金を受け取れる仕組みを解説

QYLDとは?基本情報をチェック
QYLDは、NASDAQ100指数を対象としたカバードコール戦略を採用するETFです。
そのため、通常のETFとは異なり、オプション取引を活用することで分配金を得る仕組みになっています。NASDAQ100に連動するため、AppleやMicrosoftなどのハイテク企業が多く含まれているのが特徴です。
例えば、2024年のデータではQYLDの年間分配利回りは約12%前後と高水準を維持しています。つまり、100万円投資すると年間12万円の分配金を受け取れる計算になりますね。
カバードコール戦略とは? QYLDの特徴
カバードコール戦略とは、株を保有しながらオプションを売ることでプレミアム(オプション料)を得る方法です。
QYLDはこの戦略を活用しており、価格上昇益よりも分配金重視の設計になっています。そのため、株価の値上がりを期待する投資家には向いていませんが、安定的な収益を得たい人には最適です。
QYLDの分配金の仕組みと配当利回り
QYLDの分配金は、カバードコール戦略によるオプション収益から支払われます。
そのため、市場のボラティリティ(価格変動)が高い時期ほど分配金が増える傾向があります。一方で、株価が大きく下がる局面では分配金が減るリスクもあるため注意が必要です。
以下は、QYLDの過去3年間の分配金推移です。
以下は、QYLD(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)の過去3年間の分配金推移をまとめた表です。
| 年月 | 分配金(ドル) | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年2月 | 0.165 | 最新の確認済みデータ |
| 2024年年間 | 約2.07 | 前年比 -2.9% |
| 2023年年間 | 2.033 | 前年比 -19.96% |
| 2022年年間 | 2.540 | – |
QYLDは毎月分配型のETFなので、定期的なキャッシュフローを求める投資家に人気ですね。
配当キングの投資ポートフォリオ更新📊
— あらきよ (@arakiyocom) March 9, 2025
東証版QYLD(2865)を1万株まで買い進めた結果、年間配当金額が増えました📈
カバコ買い増しはこれで一旦終了。次は増配株、優待株を狙っていく予定😎
この下落相場で資産額は数百万単位で減ってますが、くじけず株を買い進め配当額をさらに増やしたい😼 pic.twitter.com/qYBWEh1Lsv
QYLDブログで話題!投資初心者に向いている理由

少額から投資可能! 初心者でも始めやすい
QYLDは1口単位で購入できるため、少額から投資を始められます。
米国株ETFの中でも手頃な価格帯で取引されており、2024年現在の株価は約17ドル(約2,500円)前後です。そのため、初心者でも無理なく投資できるのが魅力です。
毎月の分配金が魅力! 安定したキャッシュフロー
QYLDは毎月分配金を受け取れる数少ないETFの一つです。
通常の株式投資では、配当は年2回や年4回が一般的ですが、QYLDなら毎月安定した収益を得ることが可能です。そのため、生活費の補填や老後資金として活用しやすいですね。
他の高配当ETFとの違いを比較
QYLDは高配当ETFの中でも特に分配金利回りが高いETFです。
下記の表で、代表的な高配当ETFと比較してみましょう。
他の高配当ETFとの比較
| ETF名 | ティッカー | 配当利回り | 主な特徴 | 運用会社 | 純資産 | 経費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ | 約9% | NASDAQ 100株式+カバードコール戦略 | JPMorgan | 約2.2兆円 | 0.35% |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 約7% | S&P 500株式+カバードコール戦略 | JPMorgan | 約5.2兆円 | 0.35% |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLD | 約12% | NASDAQ 100株式+カバードコール戦略 | Global X | 約6.22億ドル | 0.60% |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | XYLD | 約11% | S&P 500株式+カバードコール戦略 | Global X | 約1.93億ドル | 0.60% |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | RYLD | 約12% | ラッセル2000指数+カバードコール戦略 | Global X | 約1.34億ドル | 0.60% |
QYLDは他のETFと比べて分配利回りが高いですが、その分キャピタルゲイン(値上がり益)が期待しにくい点には注意が必要ですね。
QYLDからお小遣い頂きました✨
— パート妻なみこ@バリスタFIRE中 (@NAMIKO_45) March 5, 2025
4年ほど前に購入してから一度も滞りなく
もらえてます。ありがたや☺️ pic.twitter.com/5ChAXBX1yh
QYLDのメリット・デメリットを理解しよう

メリット① 高い分配利回りで毎月収入を得られる
QYLDの最大のメリットは、高い分配金利回りです。
10%以上の利回りを維持しているため、安定した収益を確保しやすい点が魅力です。
メリット② 分散投資が可能でリスクを軽減
NASDAQ100に分散投資しているため、個別株よりリスクが低いです。
個別銘柄への投資に比べ、ETFは複数の企業に分散されているため、リスクヘッジに有効です。
デメリット① 株価の値上がり益が期待しにくい
QYLDはオプション取引を活用するため、株価の上昇余地が制限されます。
そのため、値上がり益を重視する投資家には向いていません。
デメリット② 米国ETFのため税金の二重課税に注意
QYLDの分配金は米国の源泉徴収税(10%)が発生します。
確定申告をすることで一部還付を受けられるので、税金面の対策も考える必要がありますね。
FEPIなどのカバコ(カバードコール)ETFが沢山でてきてますけども
— るごー (@lugolugo000) March 3, 2025
最大チャートを確認してどういった商品を自分が買うのかを考えてから買うほうがいいかなあ
画像はQYLDとJEPQの比較ね
◎QYLD 約12%の配当利回り
◎JEPQ 約10%の配当利回り… pic.twitter.com/6jluA250bS
QYLDの購入方法とおすすめの証券会社

QYLDを購入できる証券会社一覧
QYLDは、国内主要証券会社で購入可能です。
例えば、SBI証券・楽天証券・マネックス証券などで取り扱いがあります。
取引手数料や最低投資額を比較
各証券会社によって手数料や最低投資額が異なります。
以下の表を参考にしてください。
以下は証券会社の取引手数料と最低投資額の比較を表形式でまとめたものです。
国内株式現物取引手数料(1約定制)
| 証券会社名 | 5万円 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| auカブコム証券 | 55円 | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 3069円 | 4059円 |
| マネックス証券 | 55円 | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1013円 | 1013円 |
| GMOクリック証券 | 50円 | 90円 | 260円 | 260円 | 460円 | 880円 | 880円 |
| SBIネオトレード証券 | 50円 | 88円 | 198円 | 198円 | 374円 | 660円 | 880円 |
単元未満株(1株単位)の最低投資額
| 証券会社名 | 最低投資額 |
|---|---|
| SBI証券 | 数百円から可能 |
| 楽天証券 | 数百円から可能 |
| ブルーモ証券 | 米国株を200円から |
おすすめポイント
- 手数料無料: SBI証券と楽天証券は国内株式取引で手数料が完全無料。
- 少額投資: SBI証券・楽天証券は1株単位で購入可能。ブルーモ証券では米国株を200円から購入可能。
- 最安手数料: GMOクリック証券やSBIネオトレード証券は小額取引において業界最安水準。
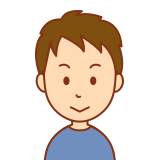
証券口座がすでにある方もNISA取引手数料無料の楽天証券がオススメですよ
- 🌏 豊富の株式の取り扱い
- 🚀初心者でも使いやすい
- 📈 NISA専用のページがわかりやすい
- 💰 楽天ポイントで投資可能
- 🚀 スマホでも簡単に売買できる便利な取引ツール
- 🏦 楽天銀行と連携すれば、スムーズに資金移動もOK!
QYLDブログで学ぶ! 投資初心者が注意すべきポイント

分配金の再投資戦略で資産を増やす方法
QYLDの分配金を再投資することで、資産を効率的に増やすことが可能です。
なぜなら、配当を受け取るだけでなく、それを再投資することで複利効果を最大限活かせるからです。特に長期投資では、この複利の力が大きな差を生みます。
例えば、QYLDに100万円を投資し、年間12%の分配金を全額再投資するとしましょう。
単純計算で、1年後には112万円、2年後には125万円…と増え、10年後には約310万円に成長します(税金や市場の変動を考慮しない場合)。
分配金を消費せず、再投資することで資産形成のスピードを加速させられますね。
再投資を効率的に行う方法
- 証券会社の「配当金自動再投資」機能を活用する
- 楽天証券やSBI証券では、米国ETFの分配金を自動で再投資できるサービスがあります。
- 分配金を貯めて、まとまった金額で買い増しする
- 価格変動の影響を受けにくくするために、一定額ごとに追加投資するのも有効な手段です。
QYLDの分配金をうまく活用しながら、長期的な資産形成を目指しましょう。
暴落時のリスク管理と対応策
QYLDは高い分配金を得られるETFですが、市場暴落時にはリスクも伴います。
特にNASDAQ100はハイテク銘柄が多く含まれるため、景気後退局面や金利上昇局面では大きく値下がりする可能性があります。
例えば、2020年のコロナショック時にはNASDAQ100全体が急落し、QYLDの株価も下落しました。
しかし、分配金は一定の水準を維持しており、長期投資家にとってはむしろ買い増しのチャンスとなりましたね。
暴落時に備えるための対応策
- QYLDだけに集中投資せず、他のETFや債券と組み合わせる
- JEPI(JPモルガンのカバードコールETF)や債券ETF(AGG、BND)を組み合わせることで、リスクを分散できます。
- 暴落時にパニック売りせず、長期目線での運用を意識する
- 過去のデータを見ると、市場は時間とともに回復する傾向があります。焦って売らず、冷静に投資を継続することが大切です。
- キャッシュポジションを確保し、買い増しのチャンスを狙う
- 市場が下落したときに買い増しできるよう、現金を一定割合持っておくことも重要ですね。
暴落は誰にとっても怖いものですが、事前に準備しておけば冷静に対処できます。リスク管理を徹底し、長期での利益を狙いましょう。
退職後の年金代わりに使うのはアリ?
QYLDを年金代わりに活用するのは「アリ」ですが、リスクを理解したうえで運用すべきです。
理由は、QYLDの分配金は高利回りですが、市場環境によっては減少する可能性があるからです。また、元本が減るリスクもあるため、全資産をQYLDに投資するのは危険です。
例えば、1,000万円をQYLDに投資し、年間12%の分配金を受け取ると仮定すると、毎月10万円のキャッシュフローが得られます。一見、安定した収入源に思えますが、QYLDの価格が下落すれば元本も減るため、持続可能性を考慮する必要がありますね。
年金代わりに活用するためのポイント
- QYLDだけでなく、他の安定資産と組み合わせる
- 例:VYM(高配当ETF)やBND(債券ETF)を併用し、リスクを分散する。
- 分配金の一部を再投資し、元本を減らさない運用を意識する
- 100%取り崩すのではなく、一部は再投資することで資産の減少を抑えられます。
- 米国ETFの税制を理解し、最適な引き出し方法を検討する
- QYLDの分配金には外国税がかかるため、確定申告で外国税額控除を活用しましょう。
結論として、QYLDは年金代わりとしての活用も可能ですが、リスク分散と適切な資産管理が必要です。無理のない範囲で活用し、長期的な安定収入を目指しましょう。
まとめ

QYLDは毎月分配金を受け取れる魅力的なETFです。
初心者でも少額から投資でき、安定したキャッシュフローを得られます。
ただし、値上がり益が期待しにくい点や税金の二重課税などのリスクもあるため、
しっかりと理解した上で投資しましょう。
長期的な運用で資産を増やす戦略が大切ですね。









コメント