※この記事は、
・株価の上下に疲れた人
・毎月の安定収入に魅力を感じる人
・インデックス投資+高配当ETFを検討している人
に向けて書いています。
毎月配当がもらえるETF「QYLD」。
「毎月の配当が自動で入る」仕組みを知ってから、
投資への向き合い方が少しラクになりました😊
この記事では、QYLDの基本情報からメリット・デメリット、そして僕が実践している“まったり資産運用術”までをわかりやすく解説します。
「QYLDはスパイス、メインはインデックスファンド」──この考え方で投資を続けたい方にぴったりの内容です💡
✅ QYLDとはどんなETF?
NASDAQ100に連動し、毎月配当を実現する「カバードコール戦略」の仕組みをわかりやすく紹介。
✅ QYLDで“まったり資産運用”を続けるコツ
放置運用でも安心して続けられる、僕自身のリアルな運用スタイルを解説。
✅ QYLDのメリット・デメリットと上手な付き合い方
初心者が注意すべき落とし穴や、インデックス投資との上手なバランスを紹介。
💰 株価の上下に疲れた僕が“毎月配当金”で安心を得た理由

🌿 値動きに一喜一憂しない「まったり投資」を目指して
結論から言うと、僕が「毎月配当金」に魅力を感じたのは、株価の上下に振り回されるのが嫌になったからです。
毎日チャートを見て一喜一憂するたびに、気持ちが落ち着かず疲れてしまいました💦
そこで僕は、「値動きを追う投資」から「安定収入を得る投資」へと考え方を変えました。
株価の動きにいちいち反応せず、安心して資産を育てられるのが“まったり投資”の魅力ですね😊
💡 毎月配当金を得る仕組みを探して辿り着いたQYLD
理由はシンプルで、「放っておいても毎月お金が入る仕組み」を作りたかったからです。
調べていく中で出会ったのが、毎月配当を出すETF『QYLD』でした📈
QYLDは“カバードコール戦略”という少し変わった仕組みで、株価が動かなくても毎月安定して配当金を受け取れるのが特徴です。
実際に運用してみると、毎月の振込通知が小さな喜びになり、「このペースでいいんだ」と思えるようになりましたね🌸
| 比較項目 | 一般的な株式投資 | QYLD(毎月配当ETF) |
|---|---|---|
| 配当頻度 | 年1〜2回 | 毎月📅 |
| 値動き | 大きく上下しやすい📉📈 | 比較的安定🌿 |
| メンタル負担 | 高い😣 | 低い😊(放置でもOK) |
| 魅力 | 値上がり益重視 | 安定した配当収入💰 |
つまり、QYLDは
「増やす投資」ではなく「受け取り続ける投資」に向いたETFなんですね。
🧘 インデックス投資中心+QYLDで心に余裕をつくる
結論として、僕はインデックス投資をメインに、QYLDをスパイスとして運用しています🌶️
なぜなら、インデックス投資は長期で資産が増えやすい一方、QYLDは“今”の安定収入をもたらしてくれるからです。
この組み合わせにしてから、「長期で育てつつ、毎月配当で心を落ち着ける」という理想のバランスが取れました。
お金だけでなく、気持ちの余裕も得られる──それが僕にとっての「毎月配当金投資」のいちばんの魅力です😊✨
💹 QYLDとは?放置でも“毎月配当ETF”がもらえる仕組み

💼 NASDAQ100に連動する高配当ETF「QYLD」
結論から言うと、QYLDはNASDAQ100指数に連動する米国ETFで、毎月配当がもらえるのが最大の特徴です💰
NASDAQ100といえば、アップルやマイクロソフトなど有名ハイテク企業が集まる指数。
QYLDはその株式をベースに、安定した分配金を投資家に届ける仕組みを持っています。
「値上がり益を狙うより、毎月の配当で安心したい」という人にぴったりのETFですね🌿
⚙️ カバードコール戦略で毎月配当金を生み出す仕組み
QYLDが毎月配当を出せる理由は、“カバードコール戦略”という特殊な運用方法にあります📈
これは、保有している株に対して「コールオプション(買う権利)」を売ることで、プレミアム(手数料収入)を得る仕組み。
つまり、株価が上がらなくても一定の収入を得られるというわけです。
ただしその代わり、大きな上昇相場では利益が限定されてしまうというデメリットもあります。
リスクとリターンのバランスを取る“落ち着いた戦略”といえますね✨
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資対象 | NASDAQ100(ハイテク株中心)💻 |
| 運用方法 | カバードコール戦略(株+オプション)⚙️ |
| 配当頻度 | 毎月📅 |
| 想定利回り | 年8〜12%(市場により変動)📊 |
| メリット | 安定した配当が得られる💰 |
| 注意点 | 値上がり益は限定される⚠️ |
🌸 利回り8〜12%!毎月配当ETFの中でも高水準
QYLDの魅力は、なんといっても年間8〜12%という高い配当利回りです💵
100万円を投資すれば、年間8〜12万円ほどの配当が期待でき、月に約7,000〜1万円が振り込まれる計算になります。
この数字は、他のETFや投資信託と比べてもかなり高い部類に入ります。
もちろん市場環境によって変動しますが、「毎月少しずつ入ってくる安心感」は何ものにも代えがたいですね😊
QYLDはやめとけ?それでも選ばれる3つのメリット【毎月配当ETF】

💵 ① 高配当で毎月安定したインカム収入
結論から言うと、QYLDの最大のメリットは高い配当利回りによる安定した収入です✨
QYLDは年8〜12%の分配金を出しており、毎月おこづかい感覚で配当を受け取れます。
たとえば100万円を投資すると、月に約7,000〜1万円前後の配当金が振り込まれる計算になります💰
この「毎月入ってくる安心感」は、他のETFではなかなか得られない魅力ですね😊
| 投資額 | 想定利回り | 年間配当額 | 月あたり配当額(目安) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 約8% | 約8万円 | 約6,600円 |
| 200万円 | 約10% | 約20万円 | 約16,600円 |
| 500万円 | 約12% | 約60万円 | 約50,000円 |
🌿 ② 値動きがマイルドで精神的にラク|QYLDは「まったり運用」向き
理由として、QYLDは株価の上下が比較的穏やかという特徴があります。
これは、カバードコール戦略によって値動きが抑えられる仕組みになっているからです📉📈
たとえ相場が荒れても、QYLDは他のハイテク株ETFよりも安定しやすく、
「今日は上がった?下がった?」と気にしすぎずに済むので、心がラクになりますね🌸
長期投資を続けるうえで“メンタルが削られない”のは大きなメリットです。
⏳ ③ 手間がかからない“放置投資”ができる
最後に、QYLDは一度買えばほぼ放置でOKなETFです🧘♀️
個別株のようにニュースや決算を毎回チェックする必要もなく、
「買って放っておくだけで毎月配当が入る」という仕組みがとても魅力的。
僕もQYLDを保有してからは、ほぼ配当通知を確認するだけで投資が完結しています📩
忙しい人や副業をしている人にとって、“放置で続けられる資産運用”は心強いですよね。
| 比較項目 | 個別株投資 | QYLD(毎月配当ETF) |
|---|---|---|
| 銘柄管理 | 必要(業績確認など)📊 | 不要(自動運用)✅ |
| 配当頻度 | 年1〜2回 | 毎月📅 |
| 手間 | 高い💦 | 少ない🧘 |
| 継続しやすさ | 難しい | 継続しやすい🌿 |
QYLDのデメリットとは?「やめとけ」と言われる理由を正直に解説

📉 値上がり益は期待しにくい|カバードコールETFの弱点
結論から言うと、QYLDは株価の上昇による利益(キャピタルゲイン)を狙う投資ではありません。
理由は、QYLDのカバードコール戦略にあります。これは「上がる権利(コールオプション)」を売ることで収益を得る代わりに、株価上昇の利益を一部放棄する仕組みです。
そのため、相場が好調なときでも大きな値上がりは望めず、“毎月の配当を受け取ること”が主目的になります。
「長期で資産を増やしたい」よりも、「安定収入がほしい」人向けのETFといえますね🌿
💔 元本割れリスクと価格下落への備え
どれだけ配当が高くても、元本割れのリスクは避けられません。
QYLDはETF(株式型ファンド)なので、市場全体が下落すればその影響を受けて価格も下がります📉
特に2022年のようにNASDAQが下がった年には、QYLDの基準価格も大きく下落しました。
毎月配当をもらっていても、トータルでマイナスになる可能性がある点は理解しておく必要がありますね。
| リスク項目 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 元本割れ | 市場下落により価格が下がる | 分散投資・長期保有 |
| 配当減少 | オプション料の変動で減る可能性 | 無理な期待をしない |
| 為替リスク | 円高時に資産価値が減少 | 円安時はプラスにもなる💱 |
💸 為替リスク・信託報酬などのコスト負担
もうひとつの注意点は、為替変動とコスト(信託報酬)です💰
QYLDは米国ETFなので、円とドルの為替差によって受け取る金額が変わります。円高になれば評価額は下がりますが、円安なら有利に働くこともあります。
また、信託報酬(運用手数料)は年0.6%前後とやや高めで、長期で持つとじわじわパフォーマンスに影響します。
「為替リスクも含めて、ドル資産を分散保有している」と考えれば、ポジティブにとらえることもできますね😊
| コスト項目 | 内容 | 負担感 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 年0.6%程度 | やや高め⚠️ |
| 為替リスク | 円高で資産目減り | 変動リスクあり💱 |
| 税金 | 配当課税+外国税 | 控除で一部カバー可🧾 |
💬 デメリットを理解してこそ“まったり運用”ができる
QYLDには確かにリスクがありますが、仕組みを理解して付き合えば怖くはありません。
「値上がり益は限定」「配当が減ることもある」──これらを理解したうえで保有することが、まったり資産運用を続けるコツです。
僕も一時期含み損を抱えましたが、「毎月の配当が入ってくる安心感」で持ち続けられました😊
リスクを受け入れたうえで、自分に合う投資スタイルを選ぶことが大切ですね。
新NISAでQYLDは買える?結論と“それでも検討される理由”
QYLDは新NISAの対象外で、つみたて投資枠・成長投資枠のどちらでも購入できません。
新NISAは、分配金を抑えて長期で資産を増やすことを目的とした制度のため、毎月配当を行うQYLDは制度の趣旨に合わないからです。
ただし、QYLDが「新NISAで買えない=不要」というわけではありません。
新NISAが「増やす投資」だとすれば、QYLDは「受け取る投資」。
毎月の配当による安心感や、相場の上下に振り回されにくい“まったり運用”を求める人にとっては、
新NISAとは別枠(特定口座)で持つ価値があるETFと言えます🌿
実際には、
新NISAでインデックス投資信託を育てつつ、QYLDで配当を受け取る
という役割分担型の運用をしている人も多いですね。
値上がり益が少ない
→ だからメインはインデックス投資にしています
元本割れリスク
→ だからQYLDは15%程度に抑えています
💹 毎月配当ETFと投資信託の違い|QYLDはどっち向き?

💡 仕組みが違うだけで「目的」は似ている
結論から言うと、「毎月配当 投資信託」と「毎月配当ETF」は、どちらも安定した収入を目的とした商品です💰
ただし、運用の仕組みやコスト構造が異なります。
ETFは上場しておりリアルタイムで売買できますが、投資信託は1日1回の基準価額で取引される仕組みです。
どちらを選ぶかは、自分がどれだけ手間をかけたいかによって変わりますね🌿
🧾 違いの理由:ETFは“自分で運用”、投資信託は“おまかせ型”
ETFは証券取引所で株のように売買され、リアルタイムで価格が動きます📈
一方で、投資信託はファンドマネージャーがまとめて運用する“おまかせ型”です。
そのため、ETFは自分の判断で売買したい人に向き、
投資信託はプロに任せておきたい人に向いています。
僕自身は「QYLDのようなETF」で、仕組みを理解しながら運用するスタイルを選びました😊
| 比較項目 | 毎月配当 投資信託 | 毎月配当 ETF(例:QYLD) |
|---|---|---|
| 売買方法 | 1日1回(基準価額)🕐 | リアルタイム取引💹 |
| 運用者 | プロが運用(おまかせ)🧑💼 | 自分で売買(セルフ管理)🙋♂️ |
| 手数料 | やや高め💸 | 低コスト⚙️ |
| 透明性 | やや不透明 | 高い(保有銘柄公開)🔍 |
| 配当の実感 | 再投資が多い | 毎月リアルに受け取れる💰 |
🌸 僕がETFを選んだ理由
僕がQYLD(ETF)を選んだ理由は、“毎月現金が振り込まれる実感”が欲しかったからです。
投資信託のように自動再投資されるのも便利ですが、「自分の口座に配当が入る」ほうがモチベーションが上がります。
また、QYLDはネット証券を使えば手数料がほぼ無料で、好きなタイミングで買えるのも魅力です。
「見て楽しい」「続けやすい」──これが僕がETFに惹かれた大きな理由ですね😊
🧭 どちらも正解、違うのは“向き不向き”
毎月配当を受け取りたい人にはどちらも有効な選択肢です。
ただし、手軽さを重視するなら投資信託・コントロールしたいならETFが向いています。
僕のように「配当を実感しながらまったり続けたい」人には、QYLDのようなETFがちょうどいいと思います✨
自分のスタイルに合った運用法を見つけることが、長く続ける秘訣ですね。
くわしくは下記の【QYLDで毎月幸せを実感】を参考にしてください。
本題のまったり資産運用する方法を説明していきます。
🧩 QYLDはポートフォリオに入れるべき?配当生活での立ち位置

💬 QYLDは「スパイス」ポジションで使うのがベスト
結論から言うと、QYLDはポートフォリオの“主役”ではなく“スパイス”として活かすのが理想です🌶️
なぜなら、QYLDは配当収入に優れている反面、値上がり益は限定的だからです。
僕もポートフォリオの中心にはインデックスファンド(S&P500やオルカン)を置き、
QYLDは“毎月の安心収入”を生み出すサブポジションとして使っています。
このバランスが心地よく、ストレスなく投資を続けられる秘訣ですね😊
📊 インデックスファンドで増やし、QYLDで受け取る
資産を増やす目的なら、やはりインデックスファンドが最も堅実です📈
一方で、毎月のキャッシュフローを作りたい人にはQYLDがぴったり。
この2つを組み合わせることで、「増やす+受け取る」の両立が可能になります。
QYLDをポートフォリオの中に10〜20%程度組み込むだけでも、毎月の配当で気持ちがラクになりますね🌿
| 資産構成イメージ | 比率(例) | 目的 |
|---|---|---|
| S&P500・オルカンなど | 70〜80% | 長期で資産を増やす💹 |
| QYLD・JEPIなど高配当ETF | 15〜20% | 毎月配当で安定収入💰 |
| 現金・短期債など | 5〜10% | 緊急時の備え💼 |
💡 僕の“まったりポートフォリオ”公開
僕自身のポートフォリオも、インデックス中心+QYLD少なめの構成です。
QYLDは全体の約15%ほどにとどめていますが、それでも毎月配当が入る安心感があります💵
2025年からはNISA口座ではオルカン、S&P500を中心にFANG+も少し買いました。
QYLDは「生活費の補助+気持ちの安定剤」として保有中です✨
配当が入るたびに、「焦らなくていい、自分のペースで大丈夫」と思えるのがQYLDの魅力ですね🌸
🧭 バランスを意識した“二刀流”運用が最強
QYLD単体で資産を増やすのは難しいですが、インデックスと組み合わせることで最強の安定感が得られます💪
増やす部分と受け取る部分のバランスを整えることで、日々の相場に左右されずに投資を続けられます。
QYLDは「まったり配当をもらいながら心穏やかに投資を続けたい人」にこそ、ぴったりの存在だと思います😊
🧘♂️ QYLDは「まったり投資」で本領発揮|僕の運用スタイル公開

💡 分散・再投資・下落時の買い増しで“ゆるく続ける”
結論から言うと、QYLDを上手に活かすコツは、
**「分散投資」+「配当の再投資」+「下落時の買い増し」**の3点に尽きます✨
僕自身もこの3つを意識してから、日々の値動きに振り回されず、まったり投資を続けられるようになりました。
焦らず、じっくり資産を育てていくのがQYLDの正しい付き合い方ですね🌿
🌍 分散投資でリスクを軽減
理由として、QYLDは高配当ETFである一方、値上がり益は期待しづらいという特徴があります。
そのため、僕はインデックスファンド(S&P500やオルカン)と組み合わせて運用しています💹
QYLDだけに頼らず、「増やす資産」と「受け取る資産」を分けることで、心の安定も手に入ります。
| 投資スタイル | 主な目的 | 代表的な商品 |
|---|---|---|
| 成長型(増やす) | 資産の拡大📈 | S&P500/オルカン |
| 収入型(受け取る) | 毎月の配当💰 | QYLD/JEPI |
| 安定型(守る) | 価格の安定💼 | 現金/債券ETF |
分散することで、一方が下がってももう一方でカバーできるため、長期的に安定した運用ができますね😊
💸 分配金は使って“配当金の幸福感”を活かす
次に意識しているのは、配当金をつかうことです💰
QYLDの分配金は毎月入ってくるため、お金をを生む”実感が得られます。
僕は実際、受け取った配当金を使って生活費にあてたり、おいしいものを食べたり、飲んだりしています。
「もらって使う」そして、「配当金」をもらえる幸せを考えるのがポイントですね🌱
| 行動パターン | 効果 | 向いている人 |
|---|---|---|
| メインはインデックス投資 | 複利で資産が増える📈 | 長期派・育てたい人 |
| 配当金は生活費に使う | キャッシュフロー安定💵 | セミリタイア派 |
| 貯金する | リスク分散・安心感🌿 | 初心者・慎重派 |
📉 下落時はチャンスと捉えて買い増し
最後に、相場の下落を怖がらないことです📉
QYLDは価格が下がると利回りが上がるため、下落時は“買い増しのチャンス”になります。
僕も2022年の下落時に少しずつ買い増しして、今では平均取得単価を下げることができました。
「下がったら買う・焦らず待つ」──このシンプルな行動こそ、まったり投資を続ける秘訣です😊
🧭 焦らず、配当を味方にゆるく続ける
QYLDは、短期で利益を狙う商品ではなく、長期で“続ける”ためのETFです。
僕もQYLDを通じて、配当を受け取りながら「焦らず増やす」感覚を学びました。
値動きに心を揺らさず、ゆっくり資産を育てていく──それが“まったり投資”の真髄だと思います🌸
❓ QYLDに関するよくある質問(Q&A)

Q1. QYLDはどこの証券会社で買えますか?
A. SBI証券・楽天証券・マネックス証券など、主要ネット証券で購入できます💹
※米国ETFのため為替や税金の仕組みは理解が必要ですが、ネット証券なら売買自体は難しくありません。
僕は楽天証券を使っていますが、ポイント投資もできて便利ですよ✨
Q2. QYLDは初心者でも買って大丈夫?
A. はい、初心者でもOKですが!僕は初心者はインデックス投資をおすすめします😊
QYLDは「株価の上昇」ではなく「毎月配当」を目的にしたETFです。
値上がり益よりも“安定したインカム収入”を求める人に向いています。
Q3. QYLDの分配金はどれくらい?
A. 年利でおおよそ8〜12%前後が目安です💰
100万円を投資した場合、年間8万〜12万円、月に6,000〜1万円程度の配当が期待できます。
ただし、市場環境によって利回りは変動しますので、参考値として考えてくださいね。
Q4. QYLDの配当金は再投資した方がいい?
A. 再投資はオススメしません📈
QYLDは値上がりが少ないかわりに毎月配当をもらえるのがポイント。
僕も受け取った配当金を生活費やこづかいに回して、配当金の幸福感を味わった方がいいです🌱
資産増加させるのはオルカンやS&P500などのインデックス投資で時間を味方にした投資がおすすめです。
Q5. NISAでQYLDを買うのはアリ?
A. 新NISAでは購入できません。そしてメインではなくサブ運用に向いています💡
NISAの非課税枠は基本はオルカンやS&P500などの優良インデックスファンドを優先。
QYLDは「毎月配当で楽しみたい」「気持ちのゆとりを得たい」ときのスパイスとして使うのが良いと思います🌿
🌸 まとめ|QYLDで“毎月配当”を楽しみながら資産を育てよう

💡 QYLDは「心にゆとりをくれるETF」
結論から言うと、QYLDはお金の安心感を“毎月感じられるETF”です😊
価格の上昇は控えめでも、安定した配当があることで「焦らない投資」を続けられます。
僕自身、毎月の配当通知を見るたびに「今日もちゃんと働いてくれてるな」と思えるんですよね💌
🌿 長期運用と分散で“まったり続けられる”
理由はシンプルで、QYLDは高配当ETF×分散投資で精神的にもラクに続けられるからです。
メインはS&P500やオルカンなどのインデックスファンドにしつつ、
QYLDをサブとして持つことで“増やす+受け取る”のバランスが取れます。
この仕組みなら、相場が荒れてもメンタルが安定しやすいんですよ🌤️
| 投資目的 | 向いている商品 | 投資スタイル |
|---|---|---|
| 資産を増やしたい | S&P500/オルカン | 成長重視📈 |
| 安定収入がほしい | QYLD/JEPI | 配当重視💰 |
| 両方バランスよく | 両者を組み合わせる | まったり派🌿 |
💬 僕の“まったり運用”が続いている理由
僕も最初は「株価の上下に疲れた投資家」でした💦
でもQYLDを取り入れてからは、毎月配当が入る安心感で気持ちが落ち着き、
長期的な視点で資産を見られるようになりました。
毎月の配当が「心のリズム」を作ってくれる──そんな存在です。
🧭 焦らず、長く、楽しむことが一番
QYLDは短期の値上がりを狙うETFではありません。
でも、「お金が毎月入る」という確実なリズムは、投資を続ける原動力になります💪
焦らず、時間を味方にして、“まったり資産運用”を楽しんでいきましょうね🌸
📘 関連記事
💰 QYLDをやめた理由|僕が感じたデメリットと次に選んだ投資先
📊 QYLDとS&P500を比較|どっちが増えた?5年間の実績を徹底検証
💵 QYLDで毎月5万円の配当金を得るには?必要資金と現実を解説
【FANG➕とは】
FANGとは米国の巨大ネット銘柄群を指す言葉で、SNSのフェイスブック(Facebook=現Meta Platforms)、通販のアマゾン・ドット・コム(Amazon.com)、動画配信のネットフリックス(Netflix)、検索エンジンのグーグル(Google)の頭文字をつないだ造語です。情報技術やビッグデータ等を活用して、生活や産業構造を大きく変える可能性を持つ企業群で構成されています。
【楽天SCHDとは】
「楽天SCHD」は投資信託「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」の通称で、「配当利回り」と「リターン」が優れていることで話題となり、販売からわずか5営業日で残高100億円を突破した人気ファンドです。

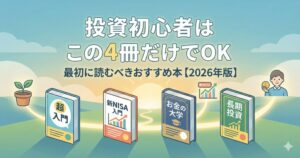

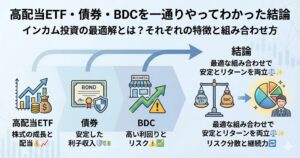





コメント