「JEPQって高配当で人気だけど、“やめとけ”って言う人も多いんだよね…🤔」
そんな声を聞いて、気になって調べた方も多いと思います。
実際、僕もQYLDを3,000株ほど保有していて、「JEPQにしておけば良かったかも…」と感じたことがあります💦
この記事では、JEPQのリスクやQYLDとの違いをわかりやすく整理していきますね。
1️⃣ 「JEPQはやめとけ」と言われる5つの理由
市場リスク・税金・為替・戦略の限界など、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
2️⃣ JEPQ・QYLD・JEPIの違いと選び方
配当利回り・リスク・戦略の違いを比較表で整理。あなたに合うETFタイプが見つかります。
3️⃣ 「やめとけ」派におすすめの代替投資法
安定志向・成長志向それぞれに合ったETFや運用スタイルを紹介します。
|
おすすめNo.1
|
|||
|---|---|---|---|
| 手数料 |
国内株・投信 無料 ポイント投資対応 |
国内株・投信 実質0円 ※ゼロ革命(条件有) |
1日50万まで 無料 NISA売買も無料 |
| ポイント |
楽天ポイント が貯まる・使える 銀行連携で金利UP |
Vポイント等 選べるポイント 投信保有で還元 |
松井証券ポイント 最大1%還元 (投信保有残高) |
| 特徴 |
初心者支持No.1 使いやすさ抜群 1株から買える |
圧倒的な商品数 豊富なラインナップ 中上級者にも人気 |
15年連続三つ星 手厚いサポート 動画学習が充実 |
|
楽天証券 公式サイト |
SBI証券 公式サイト |
松井証券 公式サイト |
「JEPQはやめとけ」と言われる5つの理由【結論】

① 市場の値動きが激しく、価格変動リスクが大きい
NASDAQ市場は成長性が高い一方で、値動きが大きく短期的な下落も起こりやすいのが特徴です。
JEPQはそのNASDAQを中心に投資するため、
「安定配当を期待していたのに、価格が下がって不安になった」
という声が出やすく、「やめとけ」と言われる原因になります。
② カバードコール戦略による“上昇益の制限”
JEPQはカバードコール戦略を使って分配金を生み出しています。
そのため、相場が急上昇した場合でも利益には上限があり、値上がり益をすべて享受できません。
「NASDAQが上がっているのに、思ったほど増えない」と感じた人が
「JEPQはやめとけ」と言うケースが多いです。
③ 税金・手数料・為替の“三重苦”
JEPQは米国ETFのため、
・米国で10%課税
・日本で20.315%課税
・米ドル建てによる為替変動
という3つのコストが発生します。
④ 上昇局面ではQYLDより弱い場面も
JEPQは「守り寄りの高配当ETF」です。
純粋にNASDAQの成長を最大限取りに行くなら、
QYLDやQQQなどの指数連動型ETFの方が有利な局面もあります。
「NASDAQ=爆発的に増える」と期待して買うと、
JEPQとのギャップを感じやすくなります。
⑤ 長期保有しないと“配当の恩恵”を受けにくい
JEPQは長期で配当を積み上げる人向けのETFです。
短期売買では、価格変動と税金の影響を強く受けてしまいます。
そのため、
「短期で結果を求める人ほど失敗しやすく、やめとけと言われやすい」
という構図になっています。
「短期で結果を求める人ほど失敗しやすい」
実際に、僕がQYLDで感じたデメリットについては
こちらの記事で正直にまとめています👇

JEPQとは?基本情報をわかりやすく解説
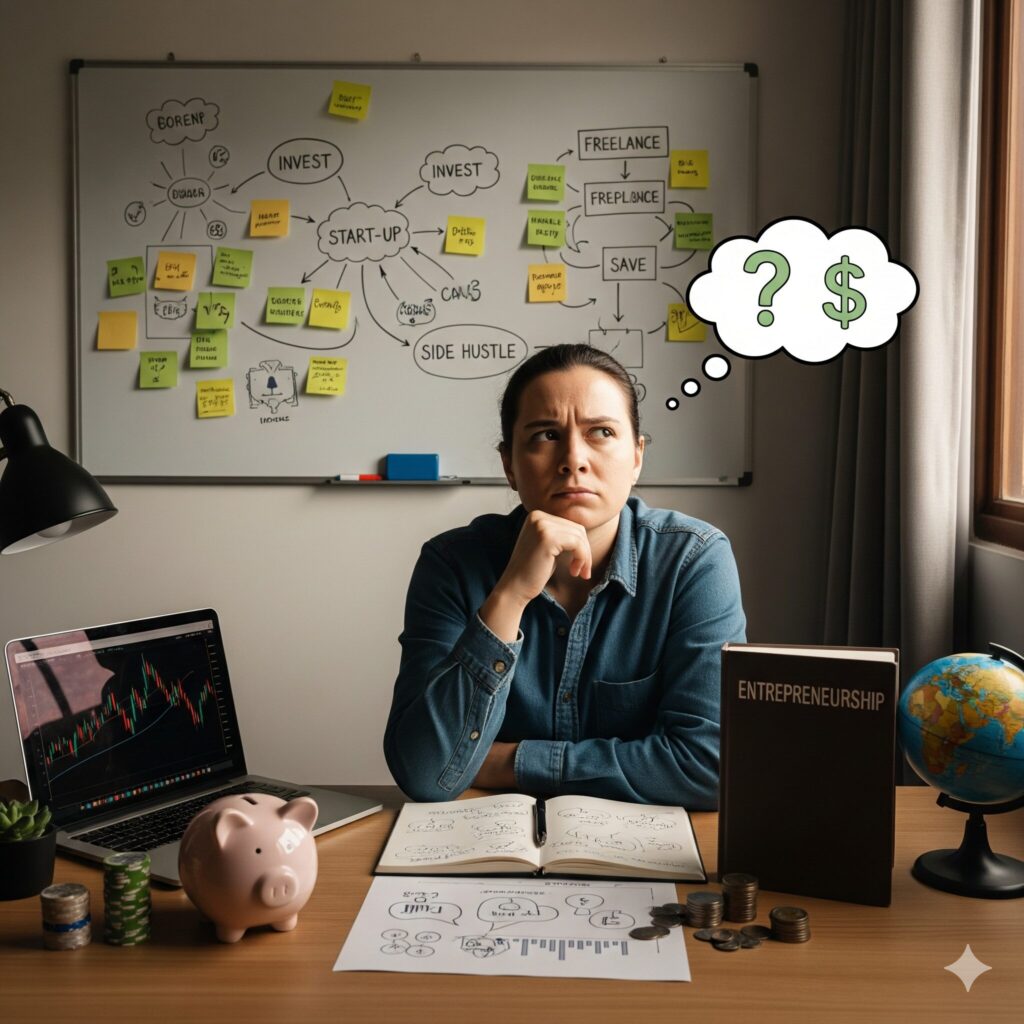
| 項目 | JEPQ | QYLD |
|---|---|---|
| 投資対象 | ナスダック上場個別株(103銘柄) | NASDAQ100指数 |
| 設定日 | 2022年5月 | 2013年12月 |
| 運用会社 | JPモルガン | グローバルX |
| カバードコール戦略 | オプションを部分的に活用 | 100%フルカバードコール |
| 分配金利回り | 約11% | 約11〜12% |
| 経費率 | 0.35% | 0.60% |
| 最大ドローダウン | -19.3% | -36.2% |
| リスクの性質 | 分散型・やや守り重視 | 攻め型・一括戦略 |
→ JEPQは“守り寄りの高配当”、QYLDは“攻めの高配当”とイメージするとわかりやすいです。
💡 結論:JEPI=守り、JEPQ=攻め
- 安定重視ならJEPI(低ボラティリティ)
- リターン重視ならJEPQ(NASDAQ中心)
JEPQは、NASDAQ100を中心に投資しつつ、
カバードコール戦略で毎月の分配金を狙う米国ETFです。
高配当を得られる一方で、
上昇益が限定される点が特徴です。
QYLDと同じく「カバードコール戦略」を用いていますが、銘柄構成や収益構造には大きな違いがあります。
JEPQが向いている人・向いていない人

✅ 向いている人
- 毎月のインカム(配当)を安定して得たい人
- 為替リスクや配当税を理解し、長期投資できる人
- ボラティリティを許容しながらも成長株に投資したい人
❌ 向いていない人
- 短期で大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を狙いたい人
- 為替や税金などの細かい管理が面倒な人
- ETFを「買ったら放置したい」タイプ
→JEPIは安定重視、JEPQは成長+高配当を狙う人向け。
JEPQは「やめとけ」ではなく“合う人・合わない人”がハッキリするETF

「やめとけ」という声が多いのは、
- リスクを理解せずに購入してしまう
- 税金や為替を見落としていた
- 上昇益を期待しすぎていた というケースが多いからです。
にはJEPQは選択肢のひとつになるはずです。
JEPI vs. JEPQとの比較

💹 JEPI vs. JEPQ 特徴比較表
| 🏷️ 項目 | 🛡️ JEPI | 🚀 JEPQ |
|---|---|---|
| 投資対象 | 📊 S&P500指数の低ボラティリティ銘柄 | 💻 NASDAQ100指数の大型成長株 |
| 運用戦略 | 💼 ELN(エクイティ・リンク・ノート)で安定インカムを狙う | 🎯 カバードコール戦略で高配当+成長性を両立 |
| 分配金利回り(目安) | 💰 約8%(安定) | 💸 約11%(高配当) |
| リスク特性 | ⚖️ 低ボラティリティで安定運用 | 📈 値動きが大きくリスクも高め |
| リターン傾向 | 🌿 安定した収益を重視 | 🔥 成長株の上昇で高リターンが期待できる |
| 主な投資先 | 🏢 安定企業中心のS&P500構成銘柄 | 💻 ハイテク・成長企業が中心 |
| 向いている投資家タイプ | 🧘♂️ 保守的で安定配当を求める人 | 💪 積極的で高配当+成長を狙う人 |
| 代表する特徴 | 🛡️ 守りのインカムETF | 🚀 攻めの高配当ETF |
🔹 ポイント: JEPIは「安定重視」、JEPQは「成長+高配当」という違いがある。
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| ✅ 毎月のインカムを安定して得たい人 | ❌ 短期で値上がり益を狙いたい人 |
| ✅ 為替リスクや税金を理解している人 | ❌ 為替や税金の管理が面倒な人 |
| ✅ 長期でじっくり投資したい人 | ❌ ETFを放置運用したい人 |
JEPQはやめとけではなく自分に合った投資なのか?

「jepq やめ とけ」という意見は、投資家それぞれのリスク観や短期的な利益追求、そして税金や手数料の負担に起因している部分があります。しかし、長期的な安定収入を目指す投資家にとっては、JEPQは十分に魅力的な選択肢となる可能性もあります。
- 長期投資を志向する方: 毎月の配当金による安定収入や、リスク分散効果を活かしながら資産形成を目指す戦略として検討する価値があります。
- 短期売買を狙う方: 市場の急上昇局面でのキャピタルゲインを重視する場合は、JEPQは適さないかもしれません。
最終的には、自分自身の投資目的、リスク許容度、そして資金計画に合わせて、複数の選択肢を比較検討することが重要です。情報収集を怠らず、常に最新の市場動向をチェックすることで、賢い投資判断につなげることができるでしょう。
JEPQが合わない人の現実的な選択肢

「JEPQはちょっと合わないかも…」と感じた場合でも、選択肢はしっかりあります。
無理に高配当ETFにこだわる必要はありません。
▶ JEPI(安定重視)
値動きを抑えつつ、毎月のインカムを得たい人には JEPI が向いています。
S&P500の中でも低ボラティリティ銘柄を中心に構成されており、
JEPQよりも価格変動が穏やかなのが特徴です。
「配当をもらいながら、なるべく精神的にラクに運用したい」
そんな人には、JEPIの方がしっくり来るケースも多いです。
▶ QQQ / S&P500(成長重視)
「配当よりも、資産を増やしたい」という人は、
QQQやS&P500連動ETFの方がシンプルで分かりやすい選択です。
特にNASDAQ100やS&P500は、
・上昇局面の恩恵をフルに受けられる
・仕組みがシンプルで長期向き
というメリットがあります。
JEPQのような戦略型ETFに不安を感じる場合は、
王道の指数連動に立ち返るのも十分アリです。
▶ NISAはインデックス一本という考え方
税制メリットを最大限活かすなら、
NISAはインデックス投資に集中するのも合理的です。
・S&P500
・オルカン(全世界株式)
などをNISAで積み立て、
JEPQやJEPIのような高配当ETFは「特定口座」で余裕資金のみ。
この 役割分担 をしている人は、実際かなり多い印象です。
結論|JEPQは「やめとけ」ではなく、合う人が限られるETF
JEPQは“やめとけ”なETFではありません。
ただし、仕組みを理解せずに買うと後悔しやすいETFです。
💬 よくある質問(Q&A)
Q1. 🤔 「JEPQはやめとけ」と言われるのは本当ですか?
A. 一部の投資家が「やめとけ」と言うのは、値動きの激しさや上昇益が限定される点を知らずに購入して後悔するケースがあるからです。リスクを理解して長期保有するなら、安定的なインカムETFとして有力な選択肢です💡
Q2. 💰 JEPQの分配金はどのくらいもらえますか?
A. 年間利回りはおおよそ9〜11%前後で推移しています。ただし、相場や為替に左右されるため、月ごとの分配金額には変動があります。再投資すれば複利効果も期待できます📈
Q3. ⚖️ JEPIとJEPQはどっちを選べばいいの?
A. 安定収益を重視するならJEPI、成長性と高配当を狙うならJEPQです。S&P500(JEPI)は「守り」、NASDAQ100(JEPQ)は「攻め」と覚えるとわかりやすいですよ😊
Q4. 🌏 為替リスクはどうすれば対策できますか?
A. 米ドル建てETFなので円高・円安の影響を受けます。為替差損を抑えるには「長期保有」+「定期買付」でドルコスト平均法を活かすのが効果的です💵
Q5. 🏦 NISAでJEPQを買っても大丈夫?
A.JEPQはNISA対象ではありません。長期で配当を再投資して資産を増やす戦略に向いています。安定重視ならJEPI、攻めるならJEPQでOKです✨
JEPQ やめとけ?まとめ

本記事では、主要キーワード「jepq やめ とけ」を軸に、JEPQの概要や運用戦略、さらには市場リスク、カバードコール戦略の限界、税金・手数料の問題などについて詳しく解説しました。
私はQYLDを保有しており、安全性を求めるならJEPQでも良いと思います。
S&P500やオルカンの投資信託をNISAで持つ二刀流でリスクを回避しています。
- 市場の変動性とリスク管理: Nasdaq市場の急変動リスクと、その対策としてのカバードコール戦略のメリット・デメリットについて触れました。
- 投資コストの重要性: 税金、手数料、為替リスクなど、海外ETFならではのコストについても詳しく解説し、投資家が実際に受ける負担を理解することの大切さを示しました。
- 長期投資と短期売買の違い: 自分の投資スタイルに合わせた判断が必要であることを強調し、「jepq やめ とけ」という意見も一つの参考情報として捉える重要性を述べました。
最終的に、JEPQがあなたにとって最適な投資対象かどうかは、自分の投資戦略や目標、リスク管理の考え方によって異なります。多くの情報を収集し、専門家の意見や実際の投資家の体験談を参考にして、自分に合った判断を下すことが、成功する投資への第一歩です。
以上、JEPQに関する徹底解説記事でした。この記事が、あなたの投資判断の一助となり、安心して資産運用に取り組むための参考になれば幸いです。最新の市場動向や経済情勢を常にチェックし、自分にとって最適な投資戦略を構築していきましょう。
関連記事
- 🆚 QYLDとS&P500を比較|どっちが増えた?5年間の実績を徹底検証
- 💰 QYLD・XYLD・JEPI・JEPQを比較|毎月配当ETFの違いと選び方
- 📆 QYLDで毎月5万円の配当金を得るには?必要資金と現実を解説
- ⚠️ QYLDをやめた理由|僕が感じたデメリットと次に選んだ投資先
※本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。記事内容は筆者の独自見解であり、投資判断はご自身の責任でお願いします。


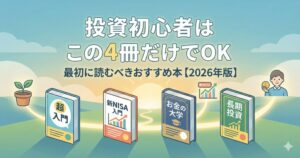

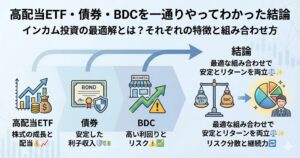




コメント